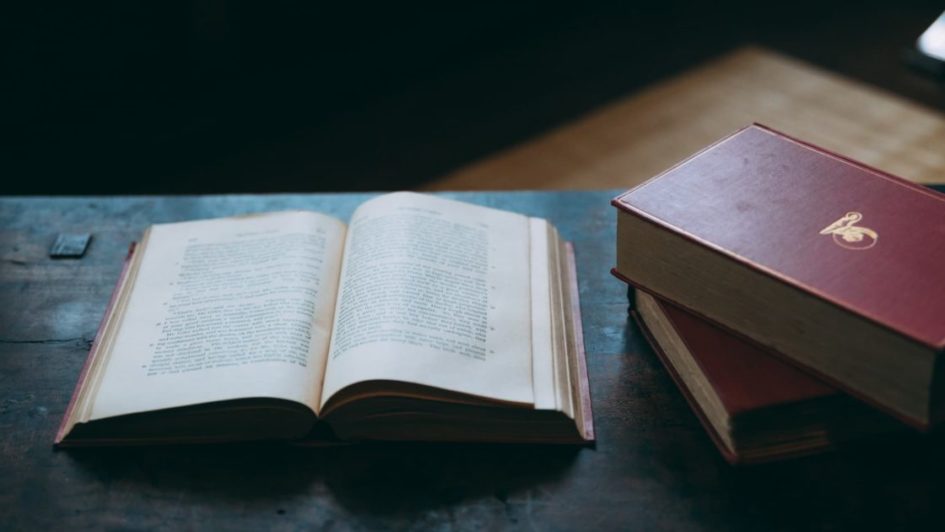1月7日は七草粥の日。子どもの頃はお正月の7日になると、家の周りで七草を探したものです。とろっとした食感と塩味、お米の旨味、野草の爽やかな味わいがとてもおいしくて、正月明けの楽しみでした。
1月7日は春の風物詩「七草粥」を食べる日
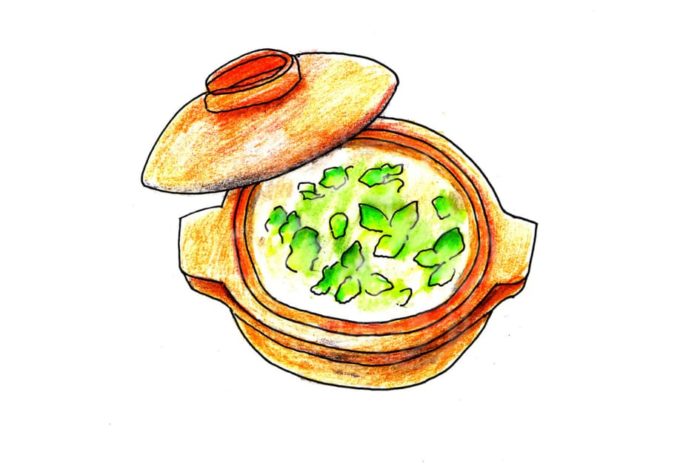
正月、1月7日は朝食に「七草粥」を食べる日です。寒さの厳しい時期にも採れる七草は仙人草とされており、それを食べることで1年間、無病息災で過ごせると考えられていました。
「土の中から顔を出したばかりの若葉を使うことで『若い気』を取り入れ、寒さに打ち勝ち病を防ごう」という意味もあったようです。
もともとは貴族の習慣だった
平安時代は宮中でのみ行われる習慣でした。当時は「米・粟・きび・ひえ・麻の実・小豆・胡麻」の穀物7つが食べられていたといわれています。

鎌倉時代に入ると、その習慣は一般庶民に広まりますが、庶民が7種類の穀物をそろえるのは難しく、あまり浸透しなかったようです。その後、七つの野草を食べて無業息災を祈る習慣に変化して、今に伝りました。
1月7日は「人日(じんじつ)の節句」
ちなみに、1月7日は五節句のひとつ「人日(じんじつ)の節句」。ひな祭りや七夕と並ぶ、五節句のひとつです。
古代中国では元日を「鶏」、2日を「狗(いぬ)」、3日を「羊」、4日を「猪」、5日を「牛」、6日を「馬」、7日を「人」、8日を「穀」の日として、その日の天気で1年の運勢を占っていました。7日は「人」のため、「人日の節句」と言います。
七草粥のレシピ
基本の七草粥のレシピを紹介しています。正月が終わり1年がスタートする特別な時期の特別なレシピ。せっかくなので、生米からコトコトていねいに炊いて、おいしいお粥を作ってみませんか?
七草粥の材料「春の七草」とは
「せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ」の七つの野草を春の七草と呼びます。

春の七草(おぼえ歌)
短歌の5・7・5・7・7のリズムで「せり、なずな/ごぎょう、はこべら/ほとけのざ/すずな、すずしろ/これぞ七草」。
リズミカルに口ずさむだけなので、ぜひ覚えてみてください。
ちなみに春の七草を漢字で書くと次のようになります。
- 芹:せり
- 薺:なずな
- 御形:ごぎょう(おぎょう)
- 繁縷:はこべら
- 仏の座:ほとけのざ
- 菘:すずな
- 蘿蔔:すずしろ
七草粥の日に七草は生えていない!?
七草粥は旧暦に行われていた行事なので、新暦の1月頭はまだ採取できない地域があります。全て自分で採取しようとするのは困難です。スーパーでセットになっているものを購入するのが手っ取り早いと思います。(スーパーで並んでいるのはビニールハウスなどで栽培されています。)
とはいえ、生えている場合もあるので、探してみるのも良いでしょう。
出会う確率が高いのは、なずな、はこべらでしょうか。その次はごぎょう、せり、ほどけのざ。すずな、すずしろは自分で育てる必要があるため購入します。
自分で採取したものを食べるのは特別感があって楽しいですし、とれたて新鮮な七草は味も良く、食が進みます。
若葉と青葉でかなり印象が異なる七草があるので、採取する場合は植物図鑑などを見てしっかり確かめてください。
春の七草一覧
では実際に。春の七草はどのような野草たちなのか、詳しく紹介していきます。
芹:せり

効果:消化促進
田んぼや川べりなど、水辺に生えています。1ヶ所に「せり(競)」合って生えることから「せり」。
おひたしやせり鍋にしてもおいしい野草です。
鉄分やビタミンを多く含む野草。似た草に毒を持つ「ドクゼリ」があります。自分で判断できない場合は、購入したほうが良いかもしれません。
薺:なずな

効果:止血。
別名「ぺんぺん草」「三味線草」。
江戸時代は冬の貴重な栄養源であり、薬草や虫よけとしても使われていました。
田んぼや畑、道のわきなど、どこにでも生える野草です。
なずなの正体を知ったときは驚きました。そこらへんに生えている「ぺんぺん草」!草取りの過程でどれだけなぎ倒したことか。この若葉って食べられるんですね…。

しっかり育ったなずな(ぺんぺん草)はこちら。若葉とかなり印象が変わります。小さなころ振り回して遊んでいました。ぺんぺん(ぺちぺち?)、って音がするんですよね。
御形:ごぎょう(おぎょう)

効果:咳止め、風邪を引きにくくする、解熱。
別名「ほうこぐさ」「母子草」。
田んぼや畑、道のわきなど、どこにでも生えています。
昔は草餅の材料になっていました。明治以降、草餅にはヨモギが使われるようになり、現在は「草餅と言えばヨモギ」へと変わっています。
「おらが世や そこらの草も餅になる/小林一茶」「両の手に 桃と桜や 草の餅/松尾芭蕉」昔の俳句に出てくる「草餅」はごぎょうの草餅です。

3月末、4月ごろに入ると、黄色い花を咲かせます。「あれが七草だったのか!」と驚くかもしれません。
繁縷:はこべら

効果:血をきれいにする。
別名「ヒヨコグサ」
畑などでよく見られます。
昔は腹痛薬や、粉上にして塩を混ぜて、歯磨き粉としても使われていました。
万葉集では波久倍良(ハクベラ)と書かれていました。現在は「はこべ」と呼ばれることの多い野草です。
タンパク質やビタミンB、Cなどが豊富。お浸しとして食べるのもおいしい野草です。昔は鶏のエサとしても使われていたようで、今でも、小鳥の栄養補給として食べさせられます。我が家ではインコに与えていました(似た植物があるため、間違えないように注意)。
2月~5月くらいに白い花が咲きます。日が当たると咲き、日が陰ると閉じてしまう面白い特徴を持っています(食べるのは花が咲く前の若葉ですが…)。
仏の座:ほとけのざ

効果:胃腸を整え、食欲を増進させる。
田んぼなどに自生している、平らで放射状に広がっている野草です。
春の七草では「仏の座」と呼びますが、本当の名は「たびらこ(田平子)(コオニタビラコ)」。
3月~5月ごろに黄色い小さな花が咲きます。黄色い花と、ややギザギザの葉を持つ姿はどこかタンポポを彷彿とさせる姿です。田舎暮らしが長いですが、頻繁に出会う植物ではありません。
なお、紫色の花を咲かせる「仏の座」がありますが、それとは別の植物です。

紫色の花を咲かせる「仏の座」。七草粥に使う野草はこれではありません!
オニタビラコとヤブタビラコ
似た植物にオニタビラコ、ヤブタビラコがあります。
ほとけのざ、つまり「たびらこ(田平子)(コオニタビラコ)」は、全体的に無毛。花が咲く茎は、根本が立ち上がり頭が下がって、斜めに傾いています。
オニタビラコは軟らかい毛が生えており、茎はまっすぐ上へ直立。ヤブタビラコは、軟らかい毛があり、茎は斜めになりながらも上へとやや立ち上がっているのが特徴です。
菘:すずな

効果:咳止め、胃もたれ。
「すずな」は蕪(かぶ)のことです。
蘿蔔:すずしろ

効果:消化促進、風邪を引きにくく。
すずしろは大根のことです。白さから「清白」ですずしろと呼ぶ場合もあります。